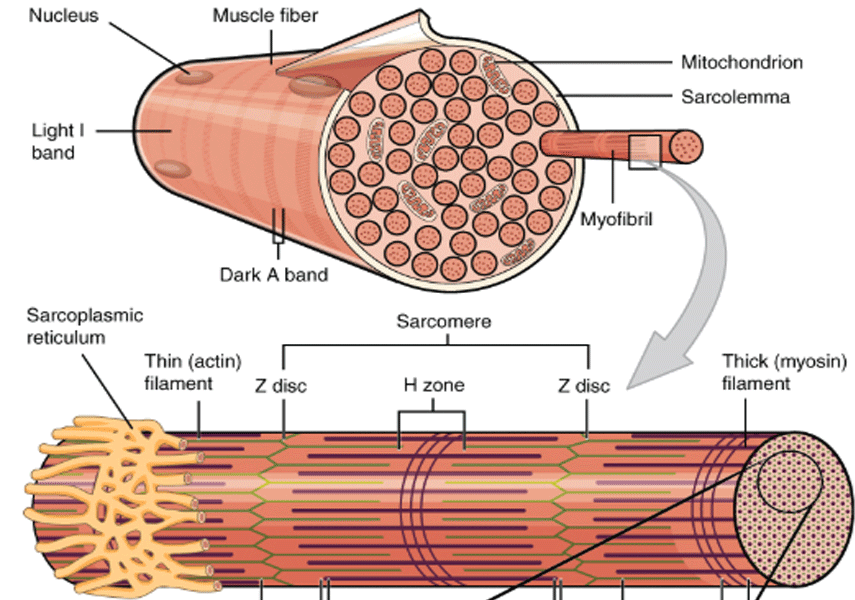
ポッピングサルコメア仮説とは
オーストラリアの電気技師David Morganは、遠心性収縮に伴う筋損傷について、損傷をもたらすのは個々のサルコメアの損傷ではなく、サルコメア間の相互作用によるものだという説を提唱しました。
この説では、わずかなサルコメア長の違いや横断面積の違いなどによって生じる筋原線維の走行に沿った小さな力の相違が、筋収縮中にわずかな力の差で各々のサルコメアを引っ張り合わせると考えられています。
ポッピングサルコメア仮説
サルコメアの発揮する力の差は、筋伸張中に異なるサルコメア長の変化を生み、長いサルコメアは短いサルコメアより伸張されサルコメア長の変化が全体の変化と比例しない部分を生み出してしまいます。筋の伸張中にこのサルコメア長の変化の相違が続き、筋原線維が重なり合わなくなる長さに達すると、より長い長さまで「はじき出される(pop)」とMorganらは提言しました。
ポッピングサルコメア仮説では、遠心性運動による筋の適応は、筋が前述したような不安定な状態にならないように、サルコメア長が長くなることから防いでいるためであると考えられています。
この適応とは、筋が長軸方向にサルコメア数を増加させ、各々のサルコメアで吸収できる伸張の程度を軽減させることであるとされています。
仮説と研究
この仮説を検証するために、Morganらはラットの大腿四頭筋、とくに中間広筋の遠心性収縮を促す下り専用の走行用トレッドミルを用いるトレーニングを実施したところ、中間広筋の筋線維の長軸方向のサルコメア数が増加したという結果が得られました。上り坂でのトレーニングにおいては、中間広筋のサルコメアは増加しないか、減少したという結果が得られたことから、遠心性収縮後にのみサルコメア数の増加がみられることを支持する結果となりました。これは遠心性運動による筋の適応と長軸方向のサルコメア数の増加というポッピングサルコメア仮説の内容と一致する形なりました。
この他にも、ポッピングサルコメア仮説に対する理論的な支持や実験的エビデンスが存在します。
現在はまだ研究段階ではありますが、この仮説への解答が出るのもそう遅くはないかもしれません。
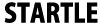
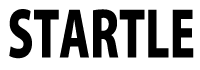







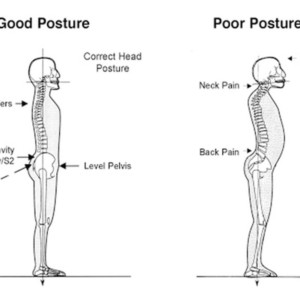


この記事へのコメントはありません。