
「肩甲上腕関節とその調整器」について考える
今日は、肩甲上腕関節とその調整器について考えます。
これは上腕骨頭の調節に関わるシステムついて書いたものですが、これらのバックグラウンドについて考えていきます。
肩甲上腕関節、いわゆる肩関節ですが、360°ほぼ自由に動く代わりに不安定な関節となっています。
関節窩に対する上腕骨頭は、例えるなら50円玉硬貨にゴルフボールがぶら下がっているようなもので、とても安定していると言えません。
それでもそれをカバーするように、関節唇や関節包といった組織が周辺を取り巻くことで、なんとか安定性が保たれています。
しかし、肩関節というのはその受け皿である肩甲骨自体も動く関節なんですね。
これが厄介なわけです。
例えば、肩甲骨がAという地点に「常にそこに」あるのであれば、上腕骨にはそこに対しての調節だけがあれば良いのです。
今よりもっと単純に簡単にコントロールできるでしょう。
しかし、自由な運動を達成するためには、肩甲骨はA地点にもA’にもA’’にもというように、目まぐるしく動きます。
つまり上腕骨頭は、常にそこにあるもの対して調節されるわけではなく、肩甲骨の相対的位置に対して調節されています。
もし肩甲骨の位置が分からなければ腕も動けませんし、肩甲骨だけが動けば筋肉の位置関係も変わりますよね。
そこで関節窩と上腕骨頭の位置関係を調整するシステムが必要になるのです。
それに働くのが、主に関節包靱帯や回旋筋腱板といった組織と神経系なわけです。
根本的には、通常は主に筋が安定性を与えていると考えます。
これには回旋筋腱板だけではなく、肩を交差する筋全てが関与すると思っても良いでしょう。
そして極端な運動の際に、靭帯が伸張され安定性をもたらします。
神経系は運動器の位置などの情報をフィードバックします。
では、なぜここまでしなければならないかというと、安定性を高めるのはもちろんのこと、関節腔内を陰圧に保ったり、関節周辺の空間を保持したりしなければならないからです。
その大きくて歪な上腕骨頭がスムーズに動くための空間を与え、かつ安定性を高めるために上腕骨頭が中心化されているわけです。
さらに、肩甲上腕関節靭帯、関節包と腱板筋による上腕骨頭の中心化、肩甲胸郭関節と静的安定性を読むとさらに理解が深まると思います。
ではまた。
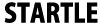
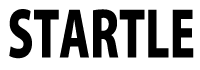







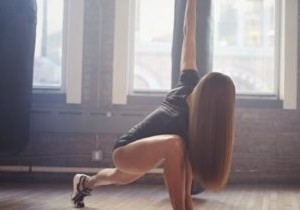


この記事へのコメントはありません。