
肥満と依存症の関係
肥満はしばしば薬物依存と似たメカニズムをもつといわれます。正確には肥満というより過食による肥満といったようなものになります。薬物依存に挙げられる特徴としては、薬物摂取を自分でコントロールできない、衝動的な行動をコントロールできないというものがあります。それは過食により肥満になってしまった人の状況とよく似ています。これは脳の報酬系の障害によるものだとされています。
病的な肥満患者においては薬物依存症患者と同じようにD2受容体が大きく減少している。
報酬系とは、「欲求が満たされたとき」「欲求が満たされると期待できるとき」などに活性化される神経回路のシステムのことです。その報酬系に関わる物質であるドーパミンの受容体のうちD2受容体の減少が依存症になるリスクを高めると考えられています。そして病的な肥満患者においては薬物依存症患者と同じようにD2受容体が大きく減少していることが分かっています。また、動物実験では高カロリーの食事を繰り返すことで報酬系の神経細胞に変化が起き、衝動的、強迫的な過食につながることが明らかになっています。ダイエットには運動が必須といいますが、運動は報酬系を刺激する代表的なものです。しっかり運動をして報酬系を活性化させれば、過食からの脱却も可能かもしれませんね。
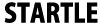
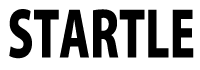

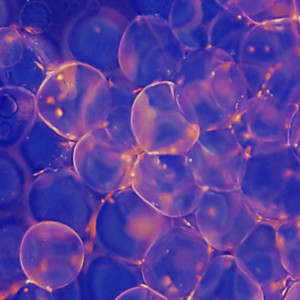








この記事へのコメントはありません。