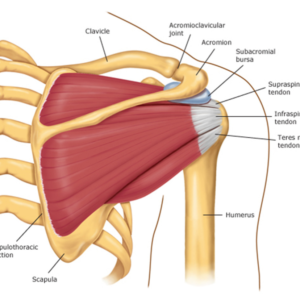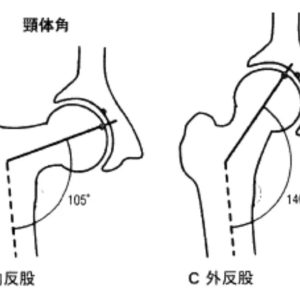脂肪は大切な栄養素の1つであり、完全に燃焼すると糖や蛋白質の2倍以上のエネルギーを放出します。
多くの動物は進化の歴史の中で飢餓や寒さに備えるために中性脂肪を貯蔵する白色脂肪細胞(一般的にいう脂肪細胞)と中性脂肪をエネルギー源として熱をつくり体温を維持する褐色脂肪細胞を発達させてきた歴史を持ちます。
つまり、白色脂肪細胞は燃料タンク、褐色脂肪細胞は熱を作るヒーターという役割と考えるとわかりやすいかもしれません。
太古の昔には、十分な食べ物を常に確保することは難しかったので、厳しい自然の中で生き延びるためには獲得した食物エネルギーを中性脂肪のかたちで白色脂肪細胞に蓄えることが必要でした。
同時に、ヒトを含む恒温動物は極寒の中でも体温を常に一定に保たなければ生きていけないので、貴重な貯蔵エネルギーである中性脂肪を効率良く燃やし熱を産み出す褐色脂肪細胞が必要であったと考えられています。
「白色脂肪細胞」と「褐色脂肪細胞」
「白色脂肪細胞」と「褐色脂肪細胞」。
これら二種類の脂肪細胞の働きは脳一交感神経系により調節されます。
例えば、寒冷環境下では皮膚に存在する感覚神経を介して「寒い!」という情報が脳に伝えられると、交感神経が刺激されてその神経末端からノルアドレナリンが分泌されます。
続いて、ノルアドレナリンは白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞の細胞膜上に存在するβ3アドレナリン受容体(β3−AR)を活性化し、白色脂肪細胞においては貯蔵されている中性脂肪を分解して脂肪酸が作られます。
一方、褐色脂肪細胞ではアンカップリングプロテイン1(UCP1)という特殊な熱産生タンパク質が活性化されて脂肪酸を燃料として熱をつくり体温の低下がが抑えられることになります。
また、食事の際にも交感神経が活性化され脂肪分解と熱産生が起こることがわかっています。
最終的には、食事で摂取するエネルギー量が身体活動で消費するエネルギー量を上回ると余ったエネルギーが中性脂肪として白色脂肪細胞に蓄積されます。
しかし、1つの白色脂肪細胞が貯め込む中性脂肪量には限界があるので、余剰のエネルギーをさらに貯め込むために脂肪前駆細胞(未分化の脂肪細胞)が分化して白色脂肪細胞の数が増えことになります。
これすなわち、肥満は中性脂肪を蓄積した白色脂肪細胞が増加して白色脂肪組織量が大きくなった状態のことをいうのです。