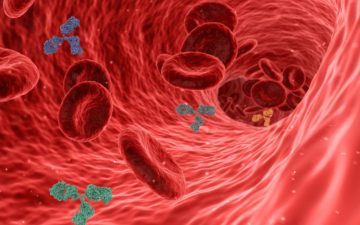レジスタンストレーニングにおける「両側性機能低下」とは、両側の筋群を同時に動員して力を発揮した際の出力が、片側ずつ発揮した力の合計値よりも低下する現象を指します。例えば、片脚ずつスクワットを行った場合の最大筋力の合計が100kgであるのに対して、両脚同時にスクワットを行うと90kgしか発揮できないという現象がこれに該当します。この現象は長らく報告されており、神経学的および運動制御の視点からさまざまな理論が提唱されてきました。
この両側性機能低下には、いわゆる「横断的特殊性(lateral specificity)」の考え方が深く関与しています。すなわち、トレーニングによる神経適応は動作の形式に特異的に現れるため、両側性の動作でトレーニングを行えば、両側同時動作時のパフォーマンス向上が顕著に見られ、一側性のトレーニングを行えば片側動作のパフォーマンスがより向上する傾向があるのです。実際に、Howard and Enoka(1991)の報告では、訓練歴のある被験者に対して一側性トレーニングと両側性トレーニングをそれぞれ行わせたところ、トレーニングの形式に対応した筋出力の向上が明確に現れたと述べられています。
このことから、スポーツの特性に応じたトレーニングの選択が重要であるといえます。例えば、重量挙げやボート競技のように両側の筋群を同時に協調的に使用する競技では、両側性トレーニングの方がより競技パフォーマンスに直結する可能性があります。一方で、自転車競技や短距離走のように左右交互に力を発揮する動作が基本であるスポーツにおいては、むしろ一側性トレーニングや、左右交互の相反的な動作を模倣したトレーニングの方が効果的であると考えられています。これを裏付けるものとして、Kuruganti and Murphy(2002)の研究では、脚の一側性トレーニング群において両側性機能低下の程度が増大し、神経系の一側支配特性がより強く表出したことが報告されています。
では、そもそもこの両側性機能低下はなぜ起こるのでしょうか。この現象を説明するために、現在までに少なくとも三つの主要な仮説が提唱されています。それが、「注意の分散」、「相反性神経支配(reciprocal innervation)」、「大脳半球間抑制(interhemispheric inhibition)」です。
まず「注意の分散」についてですが、人間の認知資源には限界があるため、両側のタスクを同時にこなそうとすると、それぞれの筋群への集中が分散し、片側に比べて出力が低下するという考え方です。この仮説は、運動制御において「注意の焦点」が筋出力に大きく影響することを示唆する文献(例えばWulf et al., 2001)にも支持されており、実際に両側動作時に注意の分配が動作効率に影響を与えることが示されています。
次に「相反性神経支配」の仮説は、両側同時に筋を収縮させようとすると、脊髄レベルで反射的な相反抑制が生じ、一方の筋が収縮する際に他方の筋への出力が抑制されるというものです。これは、通常の運動パターンにおいては一側の屈筋と伸筋が相互に抑制し合うという生理的な仕組みが、両側同時動作では不要な抑制として現れてしまうという現象を示唆します。Carroll et al.(2006)は、この反射抑制の程度がトレーニングによって緩和される可能性を示しており、経験や適応によって神経系の制御パターンも変化することが明らかになっています。
三つ目の「大脳半球間抑制」に関しては、運動野は左右の大脳半球で機能的に独立しているものの、両者の間には抑制的な相互作用が存在するという仮説に基づいています。片側の運動野が活性化すると、反対側の運動野への活動が一時的に抑制されることがあり、これが両側同時動作における出力低下の一因になると考えられています。特にこの現象は上肢の巧緻運動や協調動作に顕著であり、動作の対称性や連携を要するスポーツにおいては、パフォーマンスを左右する重要な要素となり得ます。実際に、fMRIを用いた研究(Talelli et al., 2008)では、両側同時の手指運動において大脳皮質間の抑制活動が明瞭に認められており、この神経生理学的基盤はトレーニングによって修飾される可能性もあると指摘されています。
このように、両側性機能低下という現象は、単に筋力の問題だけでなく、神経系の情報処理、注意資源の分配、そして皮質間の抑制作用など多層的な要因が複雑に関与して発現する現象であるといえます。ゆえに、競技スポーツや日常生活における動作の特性を踏まえた上で、両側性あるいは一側性トレーニングの選択とその比率を調整していくことが、効率的なパフォーマンス向上や障害予防に直結するのです。