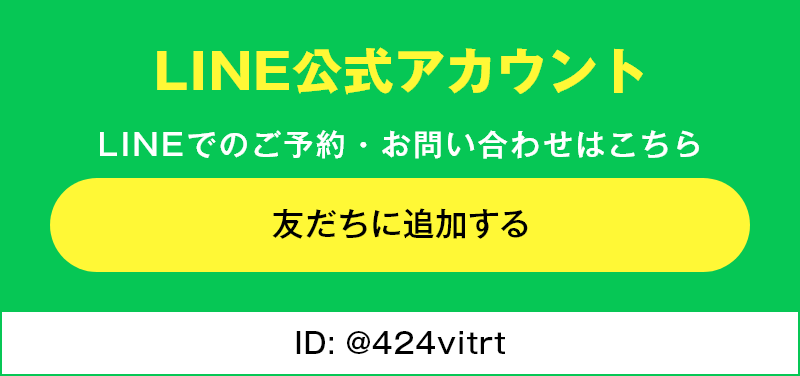自動歩行は、新生児を垂直に抱え足底を床に接地させると交互に足踏み運動が生じる原始反射で、生後2ヶ月頃この運動は認められなくなると知られています。
しかし、Thelenらは生後4週の乳児の下半身を水中に沈め浮力を与えたところ、沈めない条件下に比べ足踏み運動の頻度が増加することを報告しています。
Thelenらはこの結果について、生後2ヶ月頃足踏み運動が認められなくなるのは大脳皮質の成熟による抑制ではなく、この時期に生じる体重の増加によって相対的な筋力不足を引き起こすためとしています。
確かに環境に適応していくということを考えると、急激な成長は大きな環境要因となり、このような反応が起こるのもおかしくはないと考えられます。
一方で、行動分析学的には浮力によって足踏み運動の難易度が低くなった結果、足踏み行動が生じるようになったと解釈することもできます。
つまり身体の成熟が不十分な乳児にとって重力下での運動は難易度の高い課題だからです。
重力の影響を除くという環境の操作で乳児の行動が変化した興味深い結果であるともいえます。
他にも、Rochatらはリーチ動作に関する研究において、座位保持が不十分である乳児と座位保持を獲得した乳児のリーチ動作の頻度を比較した報告があります。
この報告では、座位保持が不十分な乳児はリーチ動作の頻度は低かったが,骨盤周辺を固定する支持を与えたところ座位保持を獲得した乳児とリーチ動作の頻度に有意差がなくなったとしています。
このことは、座位保持の難易度が体幹前屈とリーチの協調性の発達に影響を与えることを示しています。
このように難易度の変化が行動に変化をもたらすことは、乳児にかぎらずこのような行動学的特徴は成人においてもあるような気がします。
また、Rocaは18ヶ月の乳児に対し、段差の低い階段で上り下りを観察したところ、下肢を交互に出した上り下りが可能であったと報告しています。
通常、交互の階段昇降は生後36ヶ月から48ヶ月までに獲得するとされている動作になりますが、このように身体にかかる負荷を軽減させることができれば乳児の行動レパートリーに変化をもたらすことも可能であるということでもあります。
発育期の発達段階は、当然のように成長のレベルや速度によって個体差はでるものです。
現在の世論で言うと、乳児の生活環境が以前とかわり、這い這い動作を行う期間の減少、すぐにつかまり立ちなどしてしまうということも多くなり、結果として発達が十分ではない状態で次の動作獲得へ進んでしまうことも危惧されています。
結果として、身体能力の全体的な低下が進んでいると。
当然ながら、発育期の発達は漸進的に進んでいくものが望ましいと考えられますが、環境変化によって様々な感覚統合、ニューラルネットワークの構築がなされ、それによって次々と環境適応していくことを考えれば、ひとつの環境下で安全安心な生活をさせるよりは、様々な環境下に身を置き、多種多様な刺激を感受し、その刺激からさまざまな能力の発達や学習を行うことができれば、より自己組織的な発達ができるのかもしれないと思います。