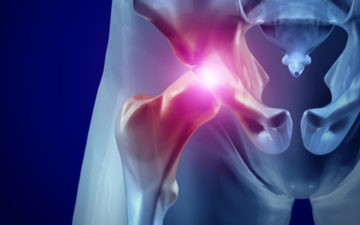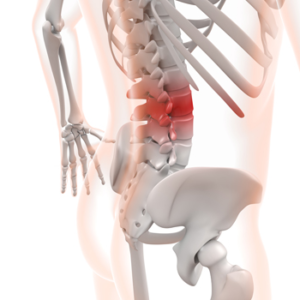ハムストリングス肉離れはダッシュや方向転換などの動作によって起こりやすい怪我です。
陸上の短距離選手が走っている時の後半に発症しやすく、再発しやすいと言われています。
原因としては、柔軟性の欠如や筋力・筋持久力の低下、筋の協調性の低下、ウォーミングアップ不足、不適切なランニングフォームなどが挙げられます。
どのようにリハビリテーションを進めていけば良いのでしょうか?
ランニング開始前
ランニング開始前は可動域の改善、痛みや腫れの緩和、筋萎縮の改善、筋力・筋持久力の強化、筋機能の安定化を目標に進めていきます。
エクササイズ内容としては、ストレッチ、筋力トレーニング、全身持久力トレーニング、患部外トレーニングを行います。
ストレッチとしては、ハムストリングスのストレッチを中心に全身行います。
スタティックストレッチ→ダイナミックストレッチ→PNFストレッチの順序で進めていきます。
筋力トレーニングはOKCトレーニング中心に行います。
順序としては、アイソメトリック→アイソキネティック→アイソトニック(コンセントリック)→アイソトニック(エキセントリック)で進め、内容としてはレッグカールやレッグエクステンション、ヒップエクステンション、ヒップフレクションなどの単関節運動を行います。
単関節運動を十分行えるようになったら、ヒップリフトなどの複合関節運動を行っていきます。
全身持久力トレーニングは患部に負担がかからないように、バイクや水中ウォーキングなどを行います。
行う理由としては、ランニングができない状態ですと心肺機能が低下し、患部が回復しても全身持久力が回復していないとスポーツや競技への復帰ができないからです。
また、運動量の低下により体重の増加が起こることもありますので、全身持久力トレーニング+食事管理が必要となっていきます。
患部外トレーニングは患部に負担がかからないように、健側の筋力トレーニング、体幹トレーニング、バランストレーニング、協調性トレーニングなどを行います。
物理療法・補装具
物理療法としては、血流を高めるためにホットパックやマッサージをトレーニング前に行い、トレーニング後にはアイシング→超音波・低周波などの物理療法を行います。
補装具としては大腿部へのテーピングやサポーターなどを着用する。
また、膝上までの保温用のスパッツも有効です。
今回はランニング開始までのリハビリテーションの流れをご紹介しました。
次回は、ランニング開始後のリハビリテーションをご紹介します。