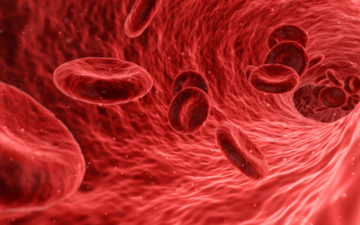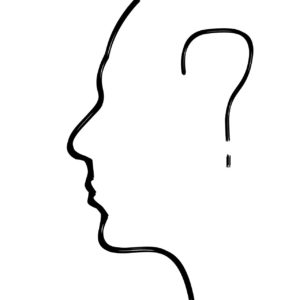私たちは普段、食事や会話の時にしか上下の歯を接触させないのが自然な状態です。通常、安静時の上下の歯は1〜3mmほど離れており、唇を閉じていても歯は触れていないのが正常とされています。ところが現代人の多くにおいて、無意識のうちに上下の歯を接触させ続ける習慣がみられます。これが「歯列接触癖(Tooth Contacting Habit:TCH)」です。このTCHは顎関節症や慢性的な肩こり、頭痛、姿勢不良といった多岐にわたる身体の不調に関与していると考えられています。
TCHの問題点のひとつは、筋肉の過緊張を引き起こす点にあります。顎を閉じるためには、咬筋や側頭筋といった咀嚼筋が持続的に働きます。東京医科歯科大学の馬場らの研究(2014年)では、上下の歯が無意識に接触している時間が1日平均17.5分を超えると、顎関節や咀嚼筋群に疲労や負担が蓄積しやすくなることが示唆されています。筋肉が緊張し続けると血流が制限され、酸素供給の低下や代謝物の蓄積によって、痛みを感じやすくなると考えられています。
さらにTCHは顎関節にも影響を及ぼします。口を閉じることで顎関節に持続的な圧力がかかると、関節内の血流や滑液の循環が悪化し、関節軟骨や靭帯組織に炎症や変性が起こりやすくなると報告されています(Okeson, 2013)。顎関節症の主な原因としては歯ぎしりや食いしばりといった顕在的な異常習癖が注目されがちですが、日中に起こる微弱な歯列接触が長時間にわたって継続されるTCHも、重大なリスク因子とされています。
このTCHの背景には、精神的なストレスや集中状態が密接に関係していることが多くの研究から示されています。たとえばKoyano(2008)の研究によると、ストレスや不安を感じている人は、歯の接触時間が長くなる傾向にあることが示されています。仕事中や勉強中、パソコン作業、スマートフォンの使用といった集中を要する状況下では、無意識に歯を接触させたままの姿勢をとっていることが多く見られます。
また、TCHは姿勢との関連性も強く指摘されています。スマートフォンやパソコンを長時間見続ける姿勢は、頸部を屈曲させ頭を前方に突き出した状態、いわゆる「前方頭位」になります。この状態では自然と口が閉じ、上下の歯が触れやすくなります。特に首が屈曲していると口を開けるために必要な下顎の運動範囲が制限されるため、無意識のうちに歯列接触が生じやすくなります。こうした頭部姿勢と口腔習癖の関係については、顎口腔機能学の分野でも広く研究が進められています。

さらに重要な点として、TCHが首や肩の筋群にも影響を与えるという点があります。顎を閉じる動作に関わる咬筋や側頭筋だけでなく、胸鎖乳突筋、僧帽筋といった頸部や肩部の筋肉が連動して活動します。これらの筋群が常に軽度の緊張状態に置かれると、慢性的な筋疲労、血流やリンパの循環不全を引き起こし、肩こりや頭痛の原因になると考えられます。事実顎関節症の患者の多くが、肩こりや首の痛みを併発していることが臨床研究でも示されています(Yap.2002)。
TCHはその発見が難しい点にも注意が必要です。歯ぎしりや食いしばりとは異なり、音もなく、本人に自覚されにくいのが特徴です。そのため肩こりや顎の違和感の原因が長らく不明のままで、結果的にTCHが見落とされているケースも少なくありません。自分自身の歯列接触の有無を確認するには、ふとした時に「いま上下の歯が触れていないか」を意識的にチェックする習慣が役立ちます。
TCHの改善には認知行動療法的なアプローチが有効とされています。具体的には「歯を離す」ことを意識させるリマインダーを用いたり、頬の筋肉を一時的に弛緩させるエクササイズを取り入れることが推奨されます。またストレスマネジメントやデスクワーク中の姿勢の見直しも、TCHの予防と改善において重要な要素です。
このようにTCHは一見些細な習慣のように見えますが、顎関節や咀嚼筋だけでなく、全身の筋骨格系や自律神経系にも影響を与えうる重要な要因です。慢性的な肩こりや顎の違和感、姿勢不良がある場合は、この無意識の歯の接触に目を向け、生活習慣を見直すことが必要かもしれません。現代のストレス社会において、TCHという見えにくい習慣が、静かに健康を蝕んでいる可能性は否定できないのです。