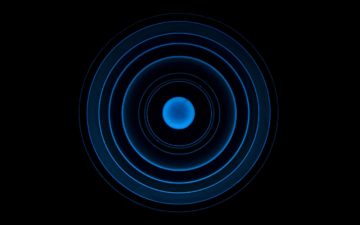前回までは疲労の原因やストレスの種類についてまとめて来ましたが、今回はストレス対策、その中でも香りによる効果に焦点を当ててみます。
香りはフレグランスやアロマなど様々な呼ばれ方をしますが、効果は幅広く、集中力アップ、風邪予防や睡眠改善にまで効果を発揮します。
今回はそんな香りが人体にどのようにして作用するのかをまとめてみます。
香りの作用
まずは香りが鼻に入り、鼻の奥にある嗅上皮から伸びている嗅繊毛という器官がニオイ成分をキャッチして脳に情報を送ります。
そして脳の視床下部という部位にまで刺激が伝わるのですが、この視床下部というところは「脳の中の脳」と言われるくらい沢山の働きがありホルモンバランスに作用したり、自律神経に影響することで身体に様々な作用を起こすという流れです。
実際に緑の香りを嗅ぐと作業能率が落ちにくく疲労感も軽減されるという効果があります。
ですので森林浴をするともちろん体を動かす気持ちよさもありますが、実は匂いからもリフレッシュできるということですね。
ちなみにみなさんも体験したことがあると思いますが、何かの匂いを嗅いだ時にある記憶が呼び起こされることがよくありますよね。
これは匂いが脳の中でも記憶を司る海馬を刺激するので匂いから記憶が引っ張り出されるということです。
香りを生活の一部にしてみよう
香りが精神面に良いのはなんとなくわかっていますが、それがどのようにして効果を発揮しているのかを理解するとさらに取り入れたくなりますね。
いい香りを発生させる代表的なものに精油がありますが、そのまま香りを楽しんで精神面に良いのはもちろん、お風呂に入れて肌を綺麗にしてくれたり、加湿器に入れて空気を殺菌してくれたり、直接肌に塗って筋肉痛を柔らげることもしてくれる精油もあります。
香りの種類は無数にあるのでここではそれぞれの効果の説明は割愛させいて頂きますが、何より自分が好きな香りを楽しむのが一番ですので、みなさんも用法用量を守りこの冬は香りの効果を存分に体感してみてください。