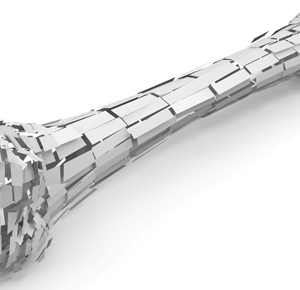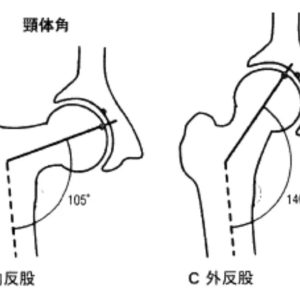むくみは見た目的にも嫌なものととらえられますが、むくみについてのある研究では「手指などの末梢関節における拘縮の発生浮腫の存在が影響しているが、重篤な拘縮へと進行した後は浮腫の存在は影響しない」と報告しています。
つまりむくみは拘縮の発生初期段階では何らかの影響を及ぼしている可能性が高いことを示唆しています。
また外傷後の炎症期の腫れは、末梢血管の透過性亢進により傷害部周囲は組織液が貯留し、同時に好中球やマクロファージ、線維芽細胞(fibroblast)などの細胞浸潤がみられ、これらにより結合組織の増殖が惹起されることがわかっています。
またこのような状態が長期化してしまうと周辺の軟部組織は低栄養・低酸素状態に強いられてしまい、壊死を生じこれを貪食する目的で細胞浸潤も活発となっていきます。
特に筋線維ではこの影響を受けやすいといわれており、再生困難なケースは消化された筋線維を置換するように結合組織の増殖が見られることがわかっています。
このようにむくみの長期化は軟部組織の器質的変化を生み出してしまうため、見た目の問題だけではなく関節可動域の発生にも直接的な影響を及ぼす可能性があります。
一方で、外傷による炎症期は、必ずと言っていいほど痛みを伴い、マクロファージなどから産生される炎症性サイトカインは痛みの増強を生み出します。
つまり、むくみのみでは関節の不動そのものは惹起されにくく、この発痛物質の産生により引き起こされる「痛み」によって、関節の不動が起こり、結果として関節の可動域制限が生じてしまうものだと考えられます。