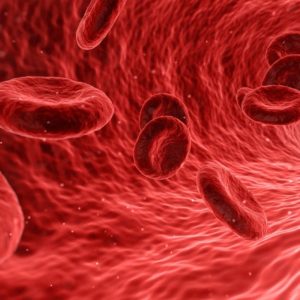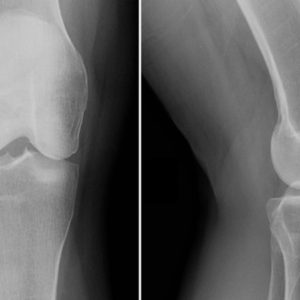エネルギー消費
1日の総消費エネルギー量は大きく分けて3つに分類されます。①基礎代謝量②食事誘発性熱産生③活動時代謝量の3つに分けられ、割合として60%・10%・30%とされています。
基礎代謝量は人が生きていく上で必要最小限のエネルギー量のことを言い、食事誘発性熱産生は食べ物を食べた時に見られるエネルギー消費の増加の事、活動時代謝量は体を動かした時に消費されるエネルギー消費のことを指します。
食事誘発性熱産生
なぜ食事誘発性熱産生が起こるかと言うと噛むこと、消化・吸収することが関わってきます。
「噛む」と言う行為は交感神経を興奮させ、熱を生産しやすくなり、エネルギー消費が高まります。
消化吸収の際にもエネルギーが消費されますが栄養素の中でもタンパク質が最も消費されるため、ダイエットしている方は積極的に摂ることおおすすめします。
なかなか体重が減らない方は噛む回数を増やしタンパク質を意識的に摂ることを心がけましょう。