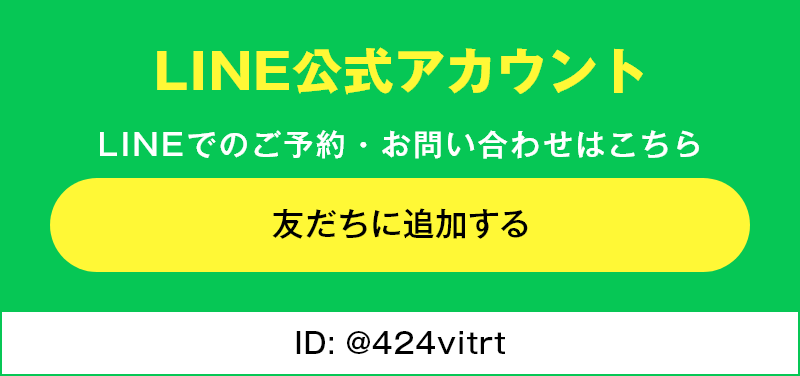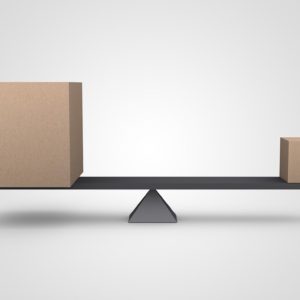「ものを動かすこと、これがヒトのできる運動のすべてである」。かつてイギリスの神経生理学者チャールズ・シェリントンは、こう簡潔に運動の本質を言い表しました。生物が外界と関わりを持つために必要な手段は、突き詰めれば「動く」ことに尽きます。そしてこの運動の唯一の実行装置が「筋」であることは、生理学的に揺るぎない事実です。
しかしながら、「動く」という現象は単純な筋収縮の繰り返しではありません。人間が日常で行う歩行や姿勢制御、さらには道具の使用などには、環境変化に応じた柔軟かつ精緻な運動調整が求められます。数百に及ぶ筋群を、状況に応じてタイミングよく適切に作動させる必要があるのです。一般には、運動制御の主役は脳であるという認識が広まっています。確かに大脳皮質、特に一次運動野や補足運動野、前運動野などが運動の企図と開始に関与していることは、神経科学の長年の研究で明らかにされています。運動の遂行には脳幹を経由して脊髄へと下行性指令が送られ、最終的に脊髄運動ニューロンから筋へと電気信号が伝えられていきます。

しかし、運動のすべてが脳の支配下にあるわけではありません。それを象徴するのが「首なし鶏マイク」の逸話です。1945年、アメリカ・コロラド州で飼われていた一羽の鶏が、誤って頭部を大きく切除されたにもかかわらず、餌をついばむような動作や歩行を数ヶ月にわたって続けたとされます。もちろん人間と鳥類の神経構造は大きく異なりますが、脳が消失しても一定の運動が持続するというこの事実は、運動制御が脳以外の部位、特に脊髄にも依存していることを如実に物語っています。
実際、20世紀初頭から脊髄の神経回路に関する研究が進むにつれ、「脊髄自体が運動パターンを生成する能力をもつ」という認識が広まりました。中枢神経系を上位と下位に分けたとき、下位にあたる脊髄には「セントラルパターンジェネレーター(CPG)」と呼ばれる神経回路網が存在します。これは、外部からの指令がなくても、一定の律動的な運動パターンを自律的に生み出す能力を持つものです。
このCPGの存在を示す象徴的な実験があります。脳幹を切除して中枢神経との連絡を絶った犬や猫の脊髄に対して、電気的な刺激を与えると、後肢がまるで歩行しているかのような律動的運動を始めるのです。こうした観察は、「運動は常に脳が細かく制御しているわけではなく、一定の運動パターンは脊髄レベルで完結しうる」という概念を裏付けました。もちろん、これは「脳が不要である」という意味ではありません。むしろ脳の役割は、環境や目的に応じてCPGの活動を呼び起こし、適切に調整することにあります。現代の神経科学では、運動制御を大きく2つの階層に分けて考えることが一般的です。ひとつは「脳による脊髄への下行性指令とその調整」、もうひとつは「脊髄レベルでの筋への直接指令とその同期化」です。
上位運動ニューロンは、抽象的な意図や環境への対応を考慮しつつ、脊髄へと大まかな指示を送ります。たとえば「右足を前に出せ」といった命令です。その後、脊髄内の神経回路がその指示を実際の運動に翻訳し、複数の筋群を適切なタイミングで協調させていくのです。

さらに脊髄内の反射機構や固有感覚からのフィードバック情報がリアルタイムで統合されることで、予測しえない環境変化にも対応可能な柔軟性が確保されます。このように脊髄はただの中継器ではなく、情報処理装置として極めて高機能な役割を果たしているのです。
こうした知見はヒトの運動障害に対するリハビリテーションや神経再生医療の戦略にも影響を与えています。たとえば、脊髄損傷患者に対する歩行訓練において、CPGを再活性化させることを目的とした電気刺激やロボットスーツによるリズム運動の導入が進められています。これは運動の一部が脊髄に内在する「プログラム」に依存しているという理論的背景があってこそ成立するアプローチです。
運動とは単に「動く」という現象ではなく、脳と脊髄の協働によって初めて成立する高度な情報処理システムの一環なのです。環境に応じて適切な筋活動を選択し、滑らかで効率的な動作を実現する。その背後には、ヒトの神経系が進化の過程で築き上げた、驚くほど精緻なメカニズムが隠されています。