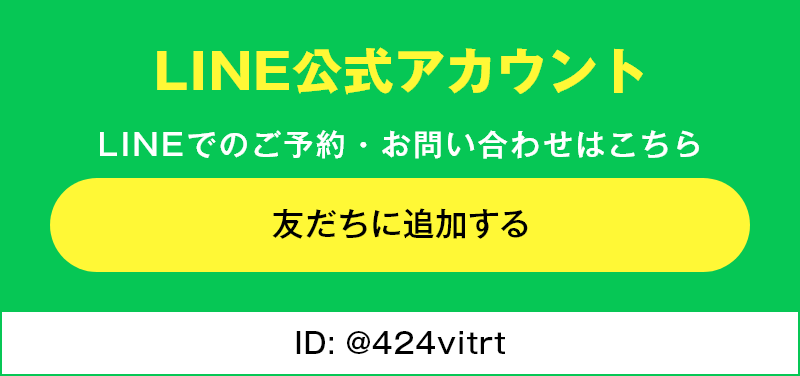最大限の運動能力を発揮する上で、私たちの前に立ちはだかる「疲労」という壁。その多くは筋肉の限界やエネルギーの枯渇など、身体的な側面から語られることが多いのですが、実のところ、まだ余力が残っているにもかかわらず動けなくなる、そんな経験をしたことがある方も少なくないでしょう。それは「中枢性疲労」と呼ばれ、身体の限界よりも前に、脳が「もうやめよう」と判断してしまう現象です。
中枢性疲労とは、脳や神経系に由来する感覚的な疲れであり、運動の継続を困難に感じさせる根本的な原因の一つと考えられています。この現象がなぜ起こるのか、科学の世界ではさまざまな仮説が提唱されてきました。

まずは「セロトニン仮説」が代表的です。セロトニンとは主に脳幹に分布する神経伝達物質で、気分や覚醒、痛みの感受性など、多くの生理機能に関与しています。このセロトニンはアミノ酸の一種「トリプトファン」から合成されますが、血中のトリプトファンはアルブミンというタンパク質と結びついて運ばれており、通常は脳内へ容易には入りません。
しかし長時間の持久的運動では、血中の遊離脂肪酸が増加し、アルブミンの結合部位を脂肪酸が占有することで、トリプトファンがアルブミンから解放されて血中の「遊離型トリプトファン」が増加します。この遊離型トリプトファンは脳関門を通過しやすく、同時に運動で消費される分岐鎖アミノ酸(BCAA)が減少することで、その競合輸送バランスが崩れ、より多くのトリプトファンが脳内に流入することになります。その結果、脳内でのセロトニン合成が促進され、セロトニン作動性神経の活性が高まり、眠気や無気力感といった「疲労感」を引き起こすというのがこの仮説の骨子です。
この仮説を裏づける研究は数多く報告されており、例えばBCAAの経口摂取が運動時のセロトニン合成を抑制し、パフォーマンス維持に役立つ可能性を示した論文も存在します(Blomstrand.1997)。ただし、この効果には個人差も大きく、現実のパフォーマンス改善への影響には議論が残ります。
一方、もうひとつ注目されているのが「アンモニア仮説」です。長時間あるいは高強度の運動を行うと、エネルギー源として筋グリコーゲンが枯渇し、体は代替エネルギーとして筋タンパク質を分解します。その際、アミノ酸の代謝過程で「アンモニア」が副産物として生じます。アンモニアは血液脳関門を通過しにくい物質ではありますが、大量に発生した場合はその防御機構も破られ、脳に到達します。脳内に入ったアンモニアは神経細胞の代謝を妨げ、神経伝達の効率を低下させることで意識レベルの低下や思考の鈍化、さらには中枢性の疲労感へとつながると考えられています。実際に血中アンモニア濃度の上昇と運動パフォーマンスの低下には相関があることが報告されており、この仮説にも一定の科学的根拠があります。

さらに近年では、疲労感の発生において「サイトカイン」も関与しているという知見が注目されています。サイトカインとは免疫細胞が分泌する情報伝達分子であり、本来は炎症反応や免疫応答に関与する重要な因子です。インターロイキン-1(IL-1)やインターフェロンなどのプロ炎症性サイトカインが血中に増えると、脳にも影響を及ぼし、発熱や倦怠感、意欲の低下といった「病気のときのような症状」が引き起こされることが知られています。これは風邪やインフルエンザの際に感じる強い疲労感とも一致しており、身体が外敵と戦っている間は、活動を抑えて回復を促すよう脳が働くという生理的な意味を持っているのです。
このように中枢性疲労の背景には多様な因子が複雑に絡み合っていることが分かってきました。トリプトファンとセロトニン、アンモニアによる神経毒性、そしてサイトカインによる免疫反応――それぞれが個別に作用するだけでなく、状況によっては相互に影響し合いながら、疲労という感覚を脳内で形成しているのです。疲労とは単なる「限界のサイン」ではなく、身体を守るために脳が意図的にブレーキをかける仕組みであると考えることができます。したがって、単純に「気合で乗り越える」といった根性論ではなく、そのメカニズムを理解し、うまく対処する戦略が求められます。たとえば栄養学的アプローチとして、BCAAや糖質の適切な補給、あるいは抗炎症作用を持つ栄養素の摂取などが提案されており、実践的な介入も少しずつ進んできています。
限界とは体が動かなくなることではなく、「脳がやめようと思うこと」である――。そうした視点で自らのパフォーマンスを見直すことが、より高みを目指すための第一歩になるかもしれません。