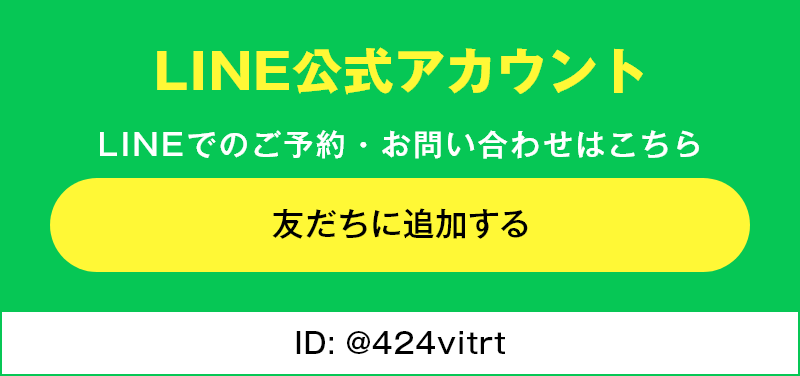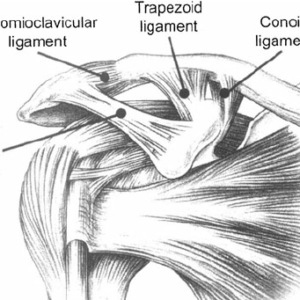「痛いから動けない」―慢性的な痛みを抱える方からよく聞かれる言葉です。けれども近年の研究によって、「動けないから痛い」が真実かもしれないという新しい視点が注目されています。運動には痛みを“抑える力”があるのです。しかもこれは一時的な気休めではなく、脳や神経系、そして筋骨格系に働きかける根本的な鎮痛効果をもたらす可能性があります。
運動療法という言葉は決して新しいものではありません。文献によれば、すでに紀元前5世紀、古代ギリシャのヒポクラテスの時代には、運動が病気の治療に用いられていたと記されています。当時は哲学と医学がまだ分離していない時代であり、「動くこと」そのものが身体と精神の調和を生み出すと考えられていました。現代になってMRIや機能的脳画像、神経生理学の進展とともに、その直感的な知見が科学的に裏付けられてきたのです。

特に注目すべきは「運動による鎮痛作用」です。これは“Exercise-Induced Hypoalgesia(EIH)”と呼ばれ、運動中および運動後に痛みの閾値が上昇し、痛みに対する耐性が増す現象を指します。このメカニズムには中枢神経系の内因性オピオイド系やカンナビノイド系、セロトニン系の活性化が関与しているとされ、薬物を用いずに身体自身が「鎮痛物質」を生成していると考えられています。まさに“動く薬”ともいえる仕組みです。
しかも興味深いのは、運動の種類によってこの鎮痛効果に大きな差がないということです。ウォーキング、サイクリング、ヨガ、レジスタンストレーニングなど、どの運動でも一定の条件を満たせば鎮痛効果が期待できるという報告が複数あります。つまり、必ずしも特別なトレーニングやハードな運動でなくても、日常的な身体活動が「痛み」に対して治療的に作用する可能性があるのです。
ただし、慢性痛患者にとっては、単純に「動けばいい」という話ではありません。近年の研究では、有痛部を無理に動かすよりも、まずは痛みのない部位、あるいは痛みに関係しない動きから始めることが効果的であると示唆されています。これは「拡散性鎮痛効果(Diffuse Noxious Inhibitory Control: DNIC)」と呼ばれる神経反応に基づいており、身体の一部で受けた感覚刺激が他の部位の痛みを抑制するというものです。
また、無痛部の運動によって全身的な鎮痛が得られる一方で、有痛部を無理に動かすと、逆に神経系が「危険信号」として認識し、脳が痛みの情報を強調してしまうリスクもあります。このような中枢性感作の状態では、痛みは単なる身体の問題ではなく、脳の認知・感情処理とも密接に関連する神経生理学的現象へと変貌しているのです。したがって運動療法の導入においては「痛みを伴わないこと」が重要な前提となります。身体が「これは安全な動きだ」と認識することで、神経系は過剰な警戒を解除し、徐々に疼痛反応を鎮めていきます。そうして段階的に、有痛部へとアプローチしていく――これが現在の運動療法の基本的な戦略です。

こうした考え方は、まさに「痛みとの対話」ともいえるでしょう。運動は筋肉を鍛えるだけでなく、痛みをめぐる身体と脳の関係性を調律する繊細なプロセスでもあるのです。現代医療のなかで、運動療法が“エビデンスに基づく治療”として位置づけられてきた理由も、ここにあります。
もちろん、運動だけですべての痛みが消えるわけではありません。ですが、運動によって身体が「痛みに勝てる」という成功体験を積み重ねていくことが、慢性痛からの回復においては何よりも重要です。薬や注射に頼るのではなく、自らの身体に“治す力”が備わっていると実感すること。それこそが、長期的な改善と生活の質の向上につながるのではないでしょうか。
今、痛みに悩むあなたにこそ、ほんの少しの「動き」から始めてほしい。運動は、あなたの身体の中に眠っていた「名医」なのかもしれません。