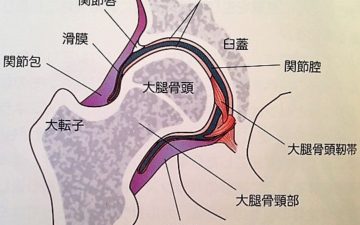運動誘発性喘息(exercise induced asthma : EIA)は運動中または運動後に症状が出現するのが特徴で、喘息患者の80%がEIAの症状に悩まされているなかで、運動時以外には症状の出ない人にも起こることがあります。
EIAは6〜8分間の激しい運動の後に起こる一過性の気道の狭窄を表し、喘息の典型的な息切れ、喘鳴、咳、胸部圧迫感に加え、胃痛や吐き気といった症状を呈することがあります。
さらに持久力の低下と、運動後の回復の遅延が起こることが示されています。
冷たく、乾燥した空気中での、換気量の多い運動が最も発作を誘発しやすく、その結果、夏のスポーツよりもウィンタースポーツの選手に発生頻度が多いとされています。
EIAは間欠的な運動よりも持続的な運動で誘発されやすく、また汚染された大気や抗原物質で満たされた空気中での運動でも頻度は高くなります。
結果的にEIAはランニングやクロスカントリースキー、アイススケートなどで非常に多いとされています。
一般に、見逃されがちであるため、パフォーマンスを大きく損なっていることがあります。
軽度から中等度の喘息患者の気道の機能は、運動の性質により変化します。
一定の負荷の運動では、はじめに軽度の気管支拡張が起こり、ついで運動開始後15〜20分で気管支収縮が起こり、運動終了時まで続きます。
対照的に、負荷が漸増する運動では気管支は進行性に収縮し、負荷が変化する運動では、強度が高いときには相対的に拡張し、負荷が低い時には相対的に収縮します。
喘息がない人の場合、運動中に気管支は拡張するか、または軽度収縮します。
気道の過敏性が減弱する気管があり、これは不応期と呼ばれています。
この不応期は2時間持続することが分かっています。
加えて、運動6〜8時間後に第2の気道の狭窄が起こることがあり、これは初めの抗原の曝露に対する炎症細胞の活性化の結果、生じるとされています。
運動により生じる一過性の気管支収縮の機序については2つの古典的な説があります。
1つは温度説で、気道の冷却と、運動歩の再加温が気管支収縮の原因であるとしたものです。
しかしこれは現在では、完全に否定されています。
もう1つは、脱水とそれによる浸透圧の上昇がEIAを引き起こすという浸透圧説です。
これを支持するエビデンスは増えていると言われています。