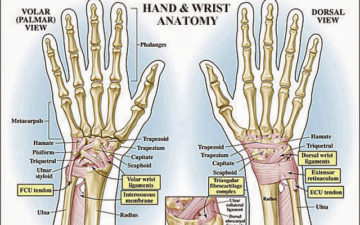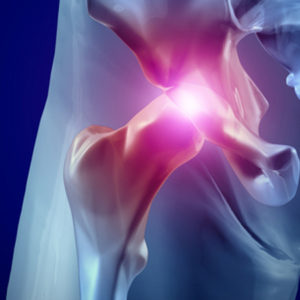ストレスがかかると、私たちの体にはさまざまな変化が起こります。これは神経系、内分泌系、免疫系が互いに密接に関係しながら、脳の指令のもとで身体と精神のバランスを保とうとするためです。
ハンス・セリエのストレス学説によれば、生体はストレスに対して特有の反応を示す一方で、共通した非特異的な反応も引き起こします。この共通の反応を「汎適応症候群」と呼び、時間の経過とともに「警告反応期」「抵抗反応期」「疲憊期」の3段階をたどるとされています。
まず、最初の警告反応期では、ストレスによって体に急激な変化が起こります。ショック状態に陥り、血圧の低下や体温の降下、筋肉の緊張の減少が見られます。また、血液が濃縮され、毛細血管の壁や細胞膜の透過性が低下し、低クロール血症や低カリウム血症といった生理的な変化が生じます。さらに、アシドーシス(体内が酸性に傾く状態)や血糖値の低下、好酸球の減少、胃や十二指腸の粘膜に炎症や出血が発生することもあります。この状態は数分から24時間ほど続くとされており、主に下垂体と副腎の働きが関与しています。体がストレスに適応しようとすると、内分泌系のうち視床下部や下垂体前葉、副腎皮質が活発に働き始めます。その結果、副腎皮質ホルモンであるコルチゾールの分泌が増え、血圧や体温、血糖値が上昇し、ストレスに対する抵抗力が高まります。また、副腎髄質からはアドレナリンが分泌され、肝臓でのグリコーゲン分解が促進されることで血糖値が上昇し、エネルギーを確保しようとするのです。

次に抵抗反応期に入ると、体はストレスと戦いながら適応しようとします。この時期には、副腎が肥大し、その活動が安定して高まり続けます。一方で、胸腺リンパ球の萎縮や白血球の増加、好酸球の減少、リンパ球の減少などが起こります。これらの変化は、免疫系にも影響を及ぼし、長期間にわたるストレスが続くと、感染症にかかりやすくなる可能性が高まります。しかし、この段階でストレス要因が取り除かれると、体は回復へ向かい、以前よりもストレス耐性が向上します。つまり、一度強いストレスにさらされ、それを乗り越えた後には、より強い抵抗力を持つようになるのです。ただし、この期間中に新たなストレスが加わると、ストレスへの適応能力が低下し、体はより弱い状態になってしまう可能性があります。
そして、長期間ストレスが続くと、最終段階である疲憊期に突入します。ここに至ると、もはや体は適応する力を失い、機能が十分に発揮できなくなります。最悪の場合、生命の維持が難しくなることもあります。慢性的なストレスにさらされ続けると、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、循環器系の疾患、糖尿病、さらにはうつ病などの精神疾患を発症するリスクも高まります。
このように、ストレスが私たちの体に及ぼす影響は非常に大きく、放置すると深刻な健康問題につながる可能性があります。そのため、適度にストレスを発散し、リラックスする時間を持つことが重要です。適切な休息や運動、バランスの取れた食事を心がけることで、ストレスによる悪影響を最小限に抑えることができます。また、自分に合ったストレスマネジメント方法を見つけることも大切です。音楽を聴いたり、趣味に没頭したり、信頼できる人と話すことなどがストレス軽減につながるかもしれません。
ストレスを完全になくすことは難しいですが、適切な対策を講じることで、体と心を健やかに保つことができます。自分自身の体の変化に注意を払いながら、健康的な生活習慣を取り入れることが、長期的に見てストレスと上手に付き合う鍵となるでしょう。