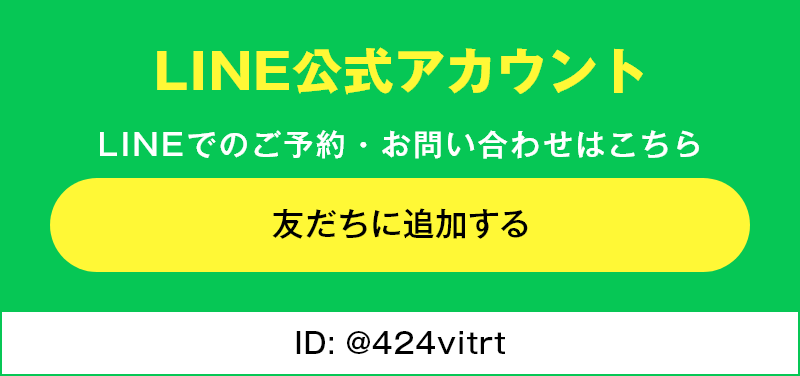地球上に生命が誕生したのは約35億年前とされています。最初に現れたのは原核生物と呼ばれる単純な構造の微生物で、核膜をもたず、細胞内小器官もない、ごく原初的な存在でした。驚くべきことに真核生物が現れるのはそれから25億年後、つまり約10億年前のこと。生命進化の歴史の7割以上を、原核生物だけが地球を支配していた時代が占めていたのです。この単純な生命体がどのようにして真核生物のような複雑な構造へと進化したのか。この謎に挑んだのが、アメリカの生物学者リン・マーギュリスでした。彼女が1967年に提唱した「細胞内共生説」は、今日では最も有力な仮説として広く受け入れられています。
この説によれば、真核生物の細胞に存在するミトコンドリアや葉緑体はもともと独立した原核生物だったと考えられています。それらは他の細胞に取り込まれたのち、排除されることなく共生関係を築き、やがて細胞内小器官として定着したというのです。実際、ミトコンドリアと葉緑体は独自のDNAをもち、その構造は環状であり、細胞核内のDNAとは異なります。また、内部のリボソームは真核細胞のものより小さく、原核生物のリボソームと一致します。こうした特徴は、かつて彼らが自立していた証ともいえます。さらに近年の研究では、シロアリの腸内に共生する原生生物が細菌と共調して運動している様子や、細胞内外に異種の細菌が複雑に共生している実例が観察され、細胞内共生の可能性を補強する事例となっています。

進化の流れを追えば、原核生物はやがて三つの系統に分かれます。核膜を発達させた原始的な真核生物、光合成能力を獲得した細菌(葉緑体の祖先)、そして酸素呼吸を可能にした細菌(ミトコンドリアの祖先)です。当時、地球には酸素がほとんど存在しませんでしたが、光合成を行う細菌が出現し、大気中に酸素を放出し始めます。これは地球環境に大きな変化をもたらしましたが、酸素は生命にとって諸刃の剣でもあります。高い反応性をもつ酸素は、DNAやタンパク質を酸化し、生物に損傷を与えるからです。
このような酸素環境のなか、ある細菌が酸素を逆に利用し、ブドウ糖を分解してATPを生み出す、いわゆる「細胞呼吸」の能力を獲得しました。これがミトコンドリアの祖先です。エネルギー効率の高いこの仕組みを取り込むことで、真核生物の祖先は酸素という脅威を味方に変えたのです。こうして、ミトコンドリアと共生する細胞が誕生し、それが複雑な生命機能を発展させる土台となりました。さらに植物の祖先では、光合成細菌との共生によって葉緑体を獲得し、太陽光を利用した有機物の合成まで可能になったのです。細胞内共生説は現在もゲノム解析や比較生物学によって検証が続けられています。ミトコンドリアや葉緑体の遺伝子は、α-プロテオバクテリアやシアノバクテリアと高い類縁性を示し、また現存する共生細菌の機能的な観察からも、かつての進化的融合の可能性が繰り返し支持されています。
生命が「共に生きる」という選択をしたこと。それが結果として、より高度で持続可能な生命のかたちを生んだ――この共生の物語は、進化の本質が競争ではなく調和にあることを静かに物語っているのです。