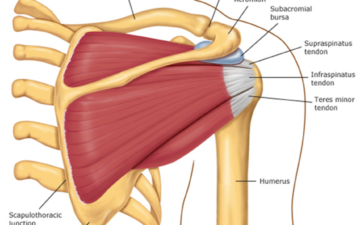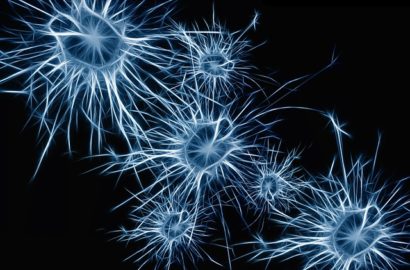人は目標を達成しようとするときや、自分の力を試す場面で、試験や検査といった「試される状況」に直面します。そして、その試験が近づくと多くの人が勉強に打ち込むようになります。しかし、その努力が極端な方向へ向かうと、睡眠を削ってまで勉強を続けるという行動に出る人も少なくありません。いわゆる「一夜漬け」ですが、これは記憶定着の観点から見ると、むしろ逆効果であることが多くの研究によって示されています。
睡眠と記憶の関係が科学的に示された最も古い研究の一つが、1924年にジェンキンスとダレンバックによって行われた実験です。彼らは無意味な単語(例:ZAT、RUKなど)を用いて、睡眠が記憶の保持に与える影響を調べました。健康な成人に10個の無意味な単語を覚えさせた後、一定時間を覚醒状態で過ごさせる群と、睡眠をとらせる群に分け、それぞれの群に記憶の想起を求めました。その結果、睡眠をとった群のほうが明らかに記憶の保持率が高かったのです。この研究から睡眠中は外部からの刺激が少ないため、記憶への干渉が起きにくく、忘却が進みにくいという「干渉説」が提唱されました。
しかしその後の研究によって、睡眠は単に記憶を守っているだけではなく、記憶を「強化し、固定化する」能動的なプロセスにも関与していることがわかってきました。たとえば、Walker(2002)の研究では、被験者にタイピング課題を行わせ、一定のトレーニング後に睡眠を取らせる群と、起きて過ごす群に分けて比較しました。その結果、睡眠を取った群のほうが翌日には明らかにタイピング速度と正確性が向上しており、睡眠中に運動記憶が強化されることが示されました。

また、Rasch(2013)による総説では、睡眠中における記憶の統合と再編成のメカニズムが詳細に述べられています。特にノンレム睡眠時に生じるスローウェーブ(徐波活動)や、海馬-大脳皮質間の情報再活性化が記憶の再構築に重要であることが示唆されました。つまり一度覚えた情報は、睡眠中に脳内で繰り返し再生され、それが長期記憶として皮質に保存されていくプロセスが存在するのです。
さらに興味深いのはクインティリアヌスという古代ローマ時代の思想家が、「睡眠は記憶を消すのではなく、強化する」と述べていた点です。彼は「前日はうまくできなかったことも、翌日には簡単にできるようになる。これは睡眠のおかげである」と記しています。これは2000年以上前に、現代科学がようやく証明した事実を直感的に捉えていた例と言えるでしょう。
またゲーム学習の文脈でも睡眠の効果が確認されています。Stickgold(2000)は、初心者にテトリスをプレイさせた後、睡眠中の夢や記憶を分析する研究を行い、ゲーム中に見た映像が睡眠中に夢として再現されることを報告しました。さらに、睡眠後のゲーム成績が向上していることから、視覚的な記憶が睡眠中に処理・強化されていると考えられました。
こうした記憶強化のメカニズムには、記憶の種類も関係しています。事実や知識に関する「陳述記憶」、技能や運動に関する「手続き記憶」、さらには情動的な出来事に関する「情動記憶」などが、それぞれ異なる睡眠段階と関連しているとされています。たとえば、ノンレム睡眠は主に陳述記憶の固定化に、レム睡眠は情動記憶や手続き記憶の統合に関与していると考えられています。
つまり、睡眠は単なる「休息の時間」ではなく、学習によって得た記憶を脳の中で取捨選択し、定着させるための非常に重要な「能動的なプロセス」なのです。にもかかわらず、試験前に一睡もしないで挑むという行動は、せっかくの学習成果を台無しにしかねません。記憶の定着を促進し、脳のパフォーマンスを最大限に引き出すためには、十分な睡眠が欠かせないのです。